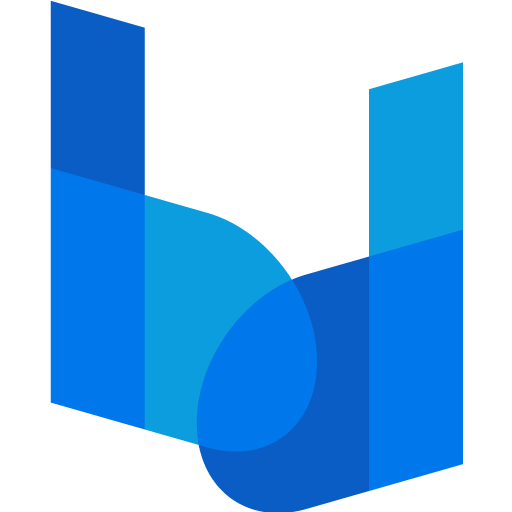サイバーエージェントの事例に見るAI導入のインパクト
先日、サイバーエージェントの広告制作チーム縮小に関するX(旧Twitter)上の投稿が話題となった。投稿によれば、同社は生成AIを導入したことで、広告制作チームの規模を「様々な職種およそ6人」から「デザイナー1人」へと大幅に縮小したという。さらに、デザイナー1人あたりの制作本数は約170本に増加し、撮影やタレント費用も削減。結果として、広告制作の効率は「5.6倍」に向上したとされている1 2。
この動きに伴い、同社ではデザイナーの新規募集を一時中止し、今後の広告業界の在り方を見極めるための戦略的な軌道修正が行われているとのことだ。ただし、これらは個人発信による情報であり、公式な発表ではないため、情報の正確性には注意が必要である。
公式情報と業界全体のトレンド
サイバーエージェントの公式発表や信頼できる報道では、広告制作チームの大幅縮小について明言はされていない。しかし、同社は広告事業においてAI技術の活用を積極的に進めており、広告売上の5~6割がAIを活用した制作によるものとされる(日経クロストレンド、2025年3月28日3)。また、2024年9月期のインターネット広告事業は売上高4,363億円、営業利益222億円と大幅な成長を記録し、AI技術への投資が業績に寄与していることがうかがえる。
さらに、動画広告市場やコネクテッドTV広告といった新たな分野への注力も進んでいる。縦型動画やショート動画など、従来とは異なるフォーマットへの対応が求められる中、制作体制の最適化や専門子会社の設立など、業界全体で「効率化」と「専門化」が加速している。
AIによる制作現場の変化とデザイナーの役割
AIの進化により、広告やWeb制作の現場では、バナーやLP、SNS用画像、動画編集などの「量産型制作業務」が急速に自動化されている。生成AIやノーコードツールまたはCanvaなどの普及によって、非デザイナーでも一定レベルのクリエイティブ制作が可能となり、従来の「作ること自体に価値がある」時代は終焉を迎えつつある。
この流れは、単なるコスト削減や効率化にとどまらない。AIによる自動化で制作コストが下がり、利益率が向上する一方で、デザイナーの職域は縮小。今後は「AIでは代替できない領域」――たとえばブランド戦略、UX設計、企画・ディレクション、クライアントとのコミュニケーション、独自性の高いアートワークなど――へのシフトが必須となる。
これからのデザイナーに求められるスキルと戦略
AI時代においても、デザイナーが生き残るためには以下のようなスキルや戦略が不可欠だ。
- AIリテラシーの習得
生成AIやノーコードツールを使いこなすことで、業務効率化や新たな表現の幅を広げることができる。AIを「脅威」ではなく「パートナー」として活用する姿勢が重要だ。 - 企画力・ディレクション力の強化
単なる制作ではなく、クライアントの課題解決やビジネスゴール達成のための企画提案力、プロジェクト全体を統括するディレクション力が価値を持つ。 - コミュニケーション力と提案力
AIにはできない「人間らしい気づき」や「共感」を武器に、クライアントやチームと信頼関係を築く力が求められる。 - 独自性・クリエイティビティの追求
テンプレート化されたデザインではなく、ブランドの世界観やストーリーを表現できる独自性の高いクリエイティブが差別化につながる。 - マーケティングやビジネスの知識
デザイン単体ではなく、広告やWebの成果に直結する視点を持つことで、より上流工程から関わることができる。
結論:デザイン業の未来と現役デザイナーの生き残り方
広告制作やWeb制作、デザイン業は、すでにAIによる自動化の波に飲み込まれている。大手企業の現場では、AI導入による効率化と人員最適化が進み、少人数で大量の制作物を生み出す体制が構築されている。今後もこの流れは加速し、「作るだけ」のデザイナーは淘汰されていくだろう。
しかし、AIでは代替できない「人間ならではの価値」を発揮できるデザイナーには、むしろ新たなチャンスが広がっている。AIを活用しつつ、より上流の企画や戦略、ブランド構築、コミュニケーションに強みを持つことで、今後もデザイン業界で活躍し続けることができる。
デザイナーとしての「生き残り戦略」は、AIを恐れるのではなく、積極的に活用し、自分自身の価値を再定義することにある。今こそ、変化をチャンスに変えるタイミングだ。
脚注
- https://journal.meti.go.jp/p/38847/ ↩︎
- https://markezine.jp/article/detail/46676 ↩︎
- https://xtrend.nikkei.com/ ↩︎