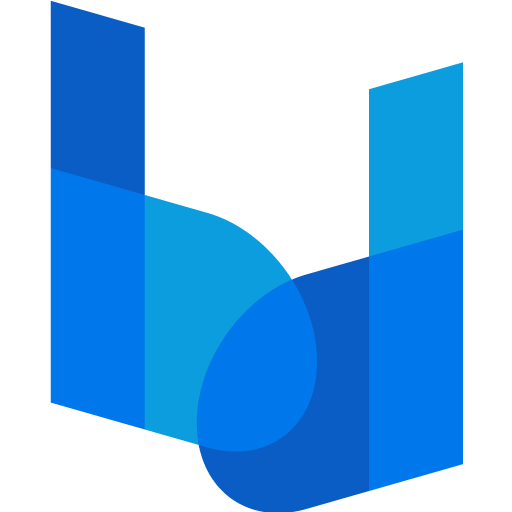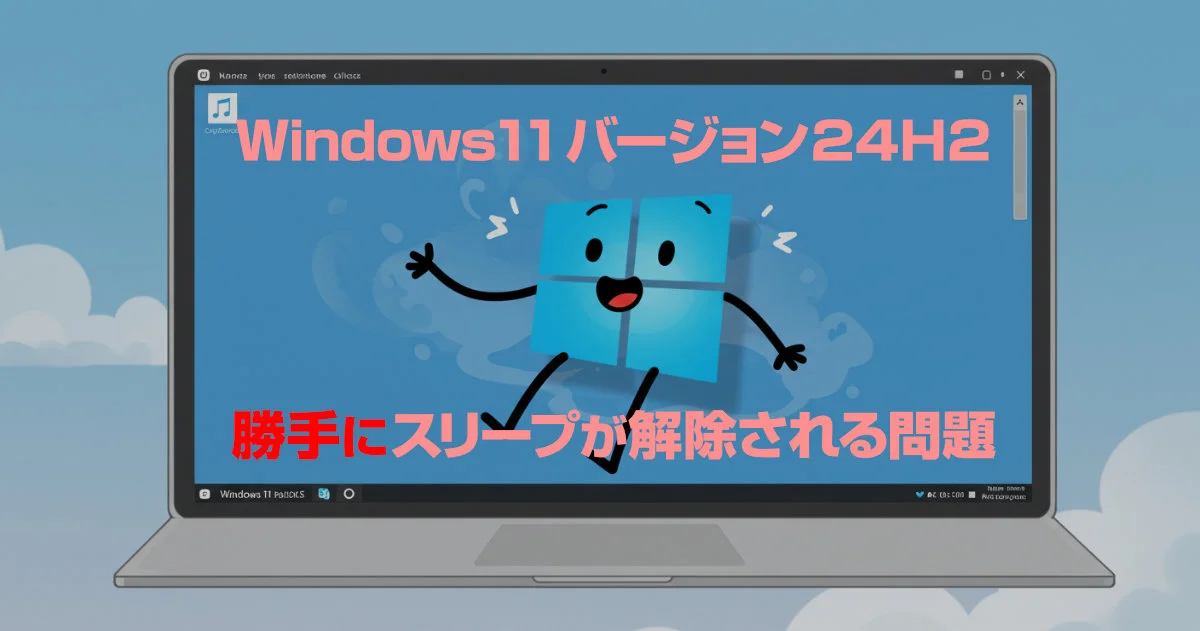さて今年も確定申告の時期がやってきた。SNSを見ると確定申告に時間をとられて、実務に身が入らないとの悲鳴が聴こえてくる。デザイナーは数字に弱い人がとても多い。また売上や経費もどんぶり勘定の人も多い。そこで私のなりのフリーランスデザイナー確定申告の方法を、少しでも参考になればとここに書いてみようと思う。
金銭的に余裕のある人は税理士に丸投げでOK!
フリーランスでも確定申告の準備をして提出まで数日を要する。そこで売上や経費の書類を丸投げするだけであとは提出までしてくれ、確定申告の時期だけ頼める税理士がいるのならその方がいい。相場はわからないが10万円くらいだろうか。金にならずつまらない事務仕事に数日を使うのは合理的でない。その間に少しでも稼いだほうがいい。タイム・イズ・マネーである。
自分で確定申告を行う
初年度は白色申告、翌年度は青色申告
しかしその10万円がない。または売上や経費、控除されるものをしっかりと認識し、貸借対照表(BS)や損益計算書(P/L)を自分で作りたい。そんな、私のような変わり者もいるだろう。
私の場合、独立した年から当然確定申告をした。しかし何がなんだかわからない状態で、税に詳しい知り合いの助言に従いまずは開業届を出し、その後に白色申告書の記入を混雑しない時期に税務署に行き教わった。家事按分の割合を質問し、経費として認められるものと認められないものを質問し、理解したつもりでなんとか自分で記入が終わり提出した。税務署の人が教えてくれる場合もあるし、確定申告提出時期が近くなると税務署内で税理士が無料で相談に乗ってくれたこともあった。開業翌年度からは控除額が大きい青色申告を行うために同時に青色申告承認申請も提出した。(税理士資格を持っていない人が記入するのは違法なので、書類の記入は自分で行うこと。)
青色申告は複式帳簿が必要になる。必要になると言うか無理。これは帳簿の書き方がわからないと難しい。これも税務署の人に教わりながらわかったようなわからないような状態で数年間なんとか記入し提出していた。しかし毎年確定申告の時期が来るとせっかく教わった記述方法を忘れている。それの繰り返しで帳簿の付け方がよくわからないのもよくないだろうと独立して数年経ってから思ったのである。
簿記学校へ通う
割と仕事が暇だった時期だったこと、複式帳簿を正確に記帳したいと常々考えていたこと、非デザイナーの友人が簿記の試験を受けるとかそんな話をしたこと、それらの理由から自分でも簿記検定を受けてみようと思ったのである。資格学校に通い日商簿記3級合格を目指した。週3日午前中2時間ほど講義を受けて、土日祝日も含め毎日2時間ほど自宅で勉強した。それを1ヶ月続けた結果余裕をもって一発合格した。
その後の流れで日商簿記2級合格も目指した。3級は商業簿記のみだが、2級はさらに上級の商業簿記と新たに工業簿記が加わる。こちらは6ヶ月のコース。3級の時と同じ勉強スケジュールなのだが、仕事が忙しくなってきて勉強時間が取れなくなってきた。そして内容も高度になる。なんとか勉強時間を捻出して日商簿記2級も一発合格できた。ここまで来たら1級を目指そうと1年間の講座もとり、講義料金も収め、何冊もあるテキストも購入した。しかし高度な内容を勉強する時間がとれず、これが1年間続くのは厳しいと判断し、初めの1ヶ月であきらめた。講座とテキスト代金はかなりの額になり無駄になってしまった。
デザイナーの場合、特に簿記の資格で仕事をとれるわけでもないので日商簿記3級の知識があれば複式帳簿の記帳には十分である。フリーランスであればむしろオーバースペックと言える。また3級で勉強した内容で企業のBSやP/Lを読むことができるし、フリーランスから会社を設立し法人化したときには勉強して得た知識が役に立つだろうとも考えていた。
私の場合は通学を選択したが、オンラインでの講義は通学時間が必要ないので今ならオンラインを選ぶだろう。講義料金も安いし。講師に質問することがあるかもと思って通学していたのだが結局一度も質問をすることはなかった。
確定申告に使うアプリ
e-taxはマイナカードの前進である住基カードが必要な時から使っていて、当初はUI/UX共に悪くものすごく使いにくかった。明らかにデザイナーが入っておらずエンジニアだけで要件定義を行いデザインは二の次だった。今でも使いやすいとはいい難いがそれでも当初よりは大分よくなったと言える。
確定申告アプリはe-taxより少し前に導入した。それ以前の数年は手書きで何度か提出していたのだが、最後BSの「資産の部」と「負債・資本の部」の合計が合わないことがしばしば起こった。どこかで計算間違いが起こっている。取引が少ない職種とは言えこれを探すに時間がかかった。そこでアプリを導入しようとなった。確定申告アプリがあればていねいな記帳の説明もあり、複式簿記がわからない人でもなんとなくできてしまう。BSの合計も合う。しかし何を記帳しているのか、仕分けは正しいのかもよくわかっていないままだと思う。自分が今なにをやっているのかをわかるためにもやはり簿記3級は有用だと思う。
導入した当時はまだクラウドによるアプリはなく店頭でパッケージを買いCD-ROMでインストールするタイプが一般的だった。初めに一番売れていた弥生のやよいの青色申告アプリを買った。その後も同じパッケージ版のやよいの青色申告アプリを何回か買った後、そろそろクラウドに以降しようと思い簡単にいくつかのアプリを比較した。やよいの青色申告(クラウド版)、freee、マネーフォワードの三つだ。無料のトライアル版があるので3つとも使ってみた。フリーランスデザイナーという職業では、単価が高い分、取引数も少ないし仕入れもない。そのような環境であると3つともそれぞれ特徴があるが大きく違いは感じられなかった。この辺りの使い勝手はそれぞれの環境や職業にもよるだろう。その中で特に理由はないがマネーフォワードを選んだが、3つとも無料トライアルが可能なので一度使ってみてから選択することをオススメする。
クリエーター系フリーランスに参考になる本
確定申告に関する本はたくさん出版されている。確定申告に関する本はあまり読んでいないのだが、その中でももっとも参考になったのが「フリーランスを代表して申告と節税について教わってきました。」きたみりゅうじ著だ。フリーランスのライター&イラストレーターであるきたみりゅうじ氏が匿名の有名税理士と会話形式で確定申告と節税を語った書籍。デザイナー、イラストレーター、ライター、エンジニア、カメラマン、編集者などのフリーランスや個人事業主と呼ばれる人におすすめの一冊。これが通常この手の書籍にはない日頃私が疑問に思っていたことをスッキリと応えてくれるぶっちゃけた内容。だから匿名。「白色申告と青色申告の手間は変わらない!」「勘定科目なんて何でもいい!?」「ぶっちゃけどこまでが必要経費?」「社会保険は国保組合を検討する!」「領収書よりもレシートのほうがいい!?」「思っていたよりもアバウトで許されるのだ!?」など、クリエーター系フリーランスの節税方法やもっと肩の力を抜いて確定申告をしましょう、ということが書かれている。
私は初版を読んだのだが、いつの間にか「令和改訂版」が出ているのではないか!手に取りやすい価格だし、会話形式なのでとても読みやすい。一読して損はない本である。