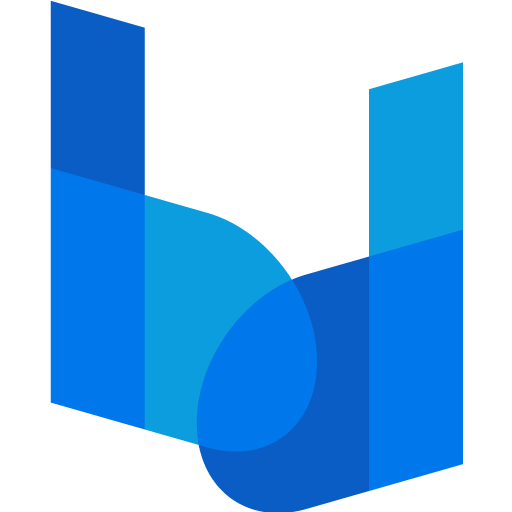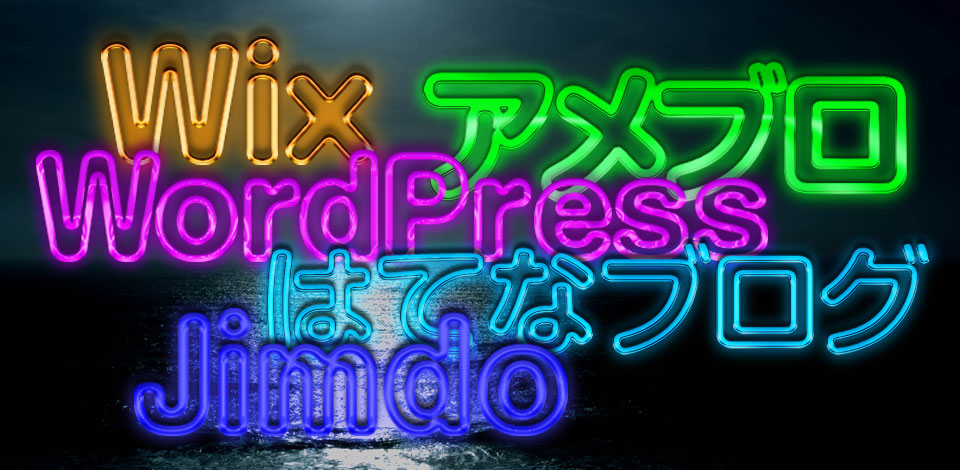氷旗のデザインはなぜこんなに目を惹くのか
夏の風物詩、「かき氷やってます!」のメッセージがはためく氷旗。その特有のビジュアル要素――白地に赤の「氷」文字、波の意匠、時に千鳥のシルエット――は、遠目にも即座に「ここでかき氷が食べられる」と分かるほど日本全国で浸透しています。このシンプルながら強烈なアイコン性は、デザインの観点からみても唯一無二といえるでしょう。
氷旗の主要デザイン要素
- 赤い「氷」の文字(白地とのコントラスト)
- 青色の波模様
- 飛び交う千鳥のイラスト
こうした要素の組み合わせは、明治時代に誕生したとされる “波千鳥” デザインがベースになっています。しかし、その詳しい起源や意図は今も謎に包まれています。
コンセプト設計とデザインアイデアの出し方
広告、ロゴ、パッケージ、UI/UX……あらゆるデザイン領域で共通して大切なのが「対象(商品・サービス)の属性」を正しく捉えること。多くの人が“いかにも”と感じるモチーフをあえて盛り込むことで、認知されやすいビジュアルが生み出されます。
具体例:
- 歯科医院 → 歯の形のアイコン
- 花屋のロゴ → 花のシルエット
- ヘヴィメタルCDジャケット → 骸骨や悪魔モチーフ
新人デザイナーの頃は“ありがち”な案をつまらなく思いがちですが、実際は「分かりやすさ」の価値が非常に高いことに気付かされます。とくに動作やサービスを示す場合には、ピクトグラム(アイコン)など徹底的に簡略化されたビジュアルが大いに役立ちます。

もし現代の店舗から「かき氷やってます!」旗のデザイン制作依頼がきたとしたら、多くのデザイナーは“かき氷のイラスト”や“涼感をイメージしたアイコン”を入れるでしょう。しかしユーザーの心には既存の氷旗のイメージが深く刻まれており、たとえば「赤」と「青」の配色がまさに「かき氷」のブランドカラーとなっています。
氷旗のデザイン要素を分解してみると



「氷旗」を分解すると上記3つの要素に分かれます。
千鳥模様 → 涼しさ、自由、動き
波しぶき → クール感、夏、涼意
氷 → 商品(かき氷)そのもの
誰が最初にデザインをしたものかは不明ですが、デザイナーの思考過程としては、
かき氷の旗のデザインを依頼された
↓
夏に冷たい(涼しい)食べ物のイメージをデザイン
↓
冷たい(涼しい)と言えば昔から“ありがち”なのは
「千鳥文様」に「波しぶき」を組みわせた「波千鳥」
↓
かき氷は氷だから「氷」と入れておけば分かる
こんな思考過程からデザインされたものと推測されます。しかし「波千鳥」が涼しさを表すというイメージが現代にはありません。それよりも何故「氷」の文字を赤にしたのか。実はそれが1番気になりました。赤は涼しさや冷たさを表す色ではないからです。では、誰もが想起する涼しい色である青にしたらどうなるでしょうか。

インパクトの源は「赤」の氷文字
一応「氷」の文字は波の色と被らないように少し薄めの青色にしました。しかしこれではインパクトがないですね。氷旗はなぜ赤い「氷」の文字なのか?青ではだめなのか?この配色の大胆さこそが、ブランドアイデンティティとしての氷旗の“強さ”を生み出しています。
- 青文字:背景の波と同化し目立たない
- 赤文字:波の青と補色関係にあり、視認性・訴求力抜群
今や「氷=赤文字」は日本で定着し、これ以外の配色では何か違和感すら覚えるほどです。
氷旗の“メジャー過ぎる”アイコンパワー
現代では、この氷旗そのものが“サイン”として機能し、これがあるだけで「かき氷」「夏」「涼しさ」といったイメージが強烈に伝わります。パッケージや販促物、関連商品デザインでも氷旗モチーフをどこかに配置するだけで消費者に直感的に「かき氷」「涼感アイテム」と認識されます。
“ありがち”デザインを侮らず活かす
尖った案も必要ですが、多くのユーザーに「分かる・伝わる」デザイン――すなわち“ありがち”な案をきちんと提案することも、現代デザインには不可欠です。氷旗デザインはその好例です。
実際の現場でデザイン案を3案提出する場合、以下のようにすれば良いでしょう
- 自分のオリジナリティーを活かした尖った案
- “ありがち”な案
- 上記2つの折衷案
経験上多くは「ありがちな案」が採用されることがほとんどです。しかし自分のオリジナリティーを出しておき「こんなこともできますよ」とクライアントに示しておくのも無駄ではありません。採用されることもゼロではないですから。
氷旗のデザインから学ぶ:現代デザイナーへのヒント
- ブランドイメージは「記号化」されるほど強くなる
- 装飾を削ぎ落とし、必要最小限の要素で「何を表すか」を明快に
- シンプルな記号性が、時代を超えて親しまれるデザインの力
“ありがち”は最高の強み!氷旗は、時代を超えて「伝わるデザイン」の洗練された実例です。